沖縄 結婚式 ウェディングLove Baileブログ
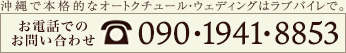
ずっと探していた藪薩(ヤブサツ)御獄にやっとたどり着くことが出来ました。台風の影響もあって、道という道もなく、草木をかき分けて、中へ中へと進んでいくと、木立の中に石の香炉が2つ、木の下に置かれています。木の間を通して久高島が見えるそうなのですが、この日は木々がなぎ倒されていて香炉の位置からは、久高島は見えませんでした。香炉は海を背後にして置いてあります。なので、久高島への遥拝所(ウ通シ)ではないかとも言われています。
この場所は、アマミクが国土作りをした琉球九御獄の一つとされ、国王一行が、東御回り(あがりうまーい)するときの拝所だったそうです。琉球九御獄とは、琉球神話においてアマミクがつくったとされる9つの御獄(安須森(アスムイ)、今帰仁城内カナヒヤブ、知念グスク、玉城グスクの雨ツヅ、斎場御獄(せいふぁーうたき)、藪薩御獄、久高クボウ森、首里城内の真玉御獄と首里オイベ)をさすとのこと。
写真の中央の海の中に見えるのは、ヤハラヅカサ。ヤハラヅカサの後方の山の上に藪薩御獄はあります。特に何があるわけでもなく、小さな香炉があって、あとは森と海があるというとてもシンプルな作りです。無我夢中で入って行って、この展望台のような開けた場所で、感動してふと思ったことは、「ハブは大丈夫だろうか…」ということ。鬱蒼とした台風後の足場の悪い場所でしたが、1ヶ月後くらいに森に枯れ葉から若葉が芽生えるようになったらさらに神聖さが増すような気がします。
国指定重要文化財に指定されており、約280年前の代表的な沖縄の農家がそのまま残されている「中村家」。沖縄本島内でこのように屋敷構えがそっくり残っている例はきわめて珍しく、当時の上層農家の生活を知る上にも貴重な遺構であるとして、昭和31年に琉球政府から、昭和47年に日本政府によって国の重要文化財に指定されています。
中村家の概要として。今から約500年前、中村家の先祖である賀氏(がうじ)は、琉球王国きっての築城家としても知られている護佐丸(中城城主)が読谷より城を中城に移した時、護佐丸の師匠として中城に移ってきたと伝えられています。その後、護佐丸・阿麻和利の乱により、護佐丸が敗れたことをきっかけに、中村家の先祖も離散の憂き目にあいますが、1720年ごろ、ようやくその家運を盛り返し、この地方の地頭職に任ぜられ、現存する中村家が出来上がったといいます。
中村家は、敷地としてはそこまで大きくはないですが、風の通るとても空気の澄んだ気持ちの良い空間です。
このふすまの向こうが、昨日私が行った時には、一番風通りが良く、気持ちのいい場所でした。風はよく通りますが、蚊などの虫はほとんどいなくて、思わずまどろんでしまうくらいの気持ちよさ☆暑い夏、沖縄の古民家で、涼を感じるのも心が動く感じがします。
台風前の土曜日に、タナガーグムイに行ってきました。タナガーとは、テナガエビのこと、グムイとは水のたまった場所という方言で、エビが棲息する川を意味するのだとか。北部をドライブしている途中で、なんとなく立ち寄った場所。車から降りると、下の方から「ゴー」という地鳴りのような音が。音に誘われながら、下へ下へと降りていく。スニーカーで、晴れの日が続く足場がしっかりした日だったから良かったけれど、結構な急斜面を10分ほど降りたところに突然姿を現す滝壺がこちら。
グムイというだけあって、水は流れる清流というよりは、深くたまって底の見えない深みがあり、水からは、少し泥の匂いがします。滝の落差は6メートルということで、普久川の中流に位置しているそうです。美しい場所ですが、川の水は海の水と違い、かなり水温が低いにもかかわらず、多くの若い方やアメリカ人の軍人さんが滝壺や、グムイで思い思いに遊んでいました。
自然に感謝して、少しおじゃまするくらいの気持ちで遊べば大丈夫だと思いますが、あまりにはしゃぎすぎてテンションが上がってしまい、溺れてしまったり転落してしまいここで命を落としてしまう方が毎年いるそうです。
人生と同じで、溺れたり転落するとなかなか這い上がるのが難しい。ここは、タナガーグムイの植物群落といって原生林のイタジイが鬱蒼と茂る場所です。またヒメユズリハ、イスノキ、イジュ、クロバイ、ヤマモモなど独特の植生が見られることから、国の天然記念物に指定されている場所です。
そういう清浄な場所なのですが、心無い利用の仕方をするために、やはりどこかで少し気味が悪い感じがします。水の淀みの中の黒さがまるで、異界と繋がっているようにも感じがしたり…。
流れる水からは、良い気が感じられるのですが、グムイ(淀み)からはやはり古事記などでも黄泉の世界とかそういう象徴になるように、どこかにひっぱられそうな、強いエネルギーがあるように感じる場所です。
本当は泳ぐような場所ではないのだと思います。今年は沖縄では台風が多く、5月には風台風により数時間で木々が壊滅的に枯れ、今回の8月の台風では40時間以上も暴風域に入り…。自然はあるがままにいるだけだと思います。それが時には人にとって都合が悪かったというだけで、攻撃しているわけでも恨んでいるわけでもない。
もともと人は「畏怖の念」から神々を信じ、世界を構築してきたと聞きます。人はあまりにも見た目では豊かになって、自分を取り囲む優しさや、強さ、畏れや様々な見えないけれど確かに存在するものをあまりにもないがしろにしてきたのかもしれません。
日本は古来より自然の猛威、氾濫や洪水、地震などと共存してきました。古事記にでてくる「八岐大蛇」の話も、蛇の悪神として描かれるヤマタノオロチは、実は洪水を意味しているといいます。
水のそばで、植物と川の水しぶき、流れる水の強さと清い冷たさを感じながら、様々なことに思いをはせた台風前のやんばるでのひと時でした。